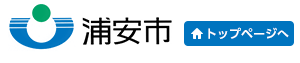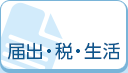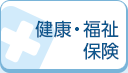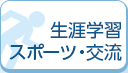男女共同参画について知りたい
男女共同参画に関連する話題を幅広く取り上げ紹介します。
固定的な性別役割分担意識
個人の能力などによって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男性は仕事、女性は家庭」や「男性は主要な業務、女性は補助的業務」などのように、性別を理由にして役割を固定的に分ける考え方をいいます。
日常の身近な場面で、「男性だから」「女性だから」などと無意識に考えていないか再確認してみましょう。
性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)
自分の経験や育った環境、社会属性によって、自分でも気づかないうちに持つようになった物事の見方やとらえ方のゆがみ・偏りのことを指します。自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識していないため、「無意識の偏見」と呼ばれます。
こんなことを聞いたり、考えたりしたことはありませんか
- 男性は人前で泣くべきではない
- 女性には女性らしい感性があるものだ
- 男性は仕事をして家計を支えるべきだ
- 女性は感情的になりやすい
- 男性は結婚して家庭を持って一人前だ
- PTAには女性が参加するべきだ
- 自治会や町内会の重要な役割は男性が担うべきだ
- 女性には理系の進路(学校・職業)は向いていない
「無意識の思い込み」の何が問題なのか
「無意識の思い込み」は、普段の会話や日常生活に溢れていて、誰にでもあるものです。ただ、あることそのものが悪いわけではありません。
問題なのは、「決めつけ」たり「押し付け」たりすることで、自分と違う考え方を受け止められず、違うアイデアを生かすことができなかったり、気づかないうちに相手を傷つけたり、差別することに繋がり、一人一人の個性や能力を生かしてその人らしく生きることができなくなることです。
自分自身の思い込みに気づくことが大切です
固定的な性別役割分担意識の解消にあたっては、性別による「無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)」に気づくことが重要です。「無意識の思い込み」を無くすことは難しいことです。しかし、自分自身の思い込みや偏見に気づき、正しい知識を身につけ、より多くの視点、より幅広い視野を持つことができるようになれば、より客観的で公平な判断ができるようになります。
性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究
内閣府男女共同参画局では、「性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果」や「チェックシート・事例集」を取りまとめています。是非ご活用ください。
格差をなくし、社会に多様な能力を生かす 「ポジティブ・アクション」
内閣府は、社会のあらゆる分野において女性の参画を進めるために、2020年代の可能な限り早期に、指導的地位に占める女性の割合が30パーセント程度になること目指し取組を進めています。さらに、指導的地位に占める女性の割合が30パーセントを超えて更に上昇し、2030年代には、性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指しています。そのため、積極的改善措置(「ポジティブ・アクション」と同義)(注記)の導入を強化するよう取り組みを進めています。
注記:「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加する機会に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること(男女共同参画社会基本法第2条第2項)」をいいます。男女間に形式的な機会の平等が確保されていても、社会的・経済的な格差が現実にある場合には、実質的な機会の平等を担保するために積極的改善措置(ポジティブ・アクション)をとることが必要です
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)
子どもができても仕事を続けたい、もっと子育てに関わりたい、仕事を続けながら親やパートナーの介護ができたら…、余暇や自己啓発にもっと時間を使いたい、ボランティア活動や地域活動に関わりたいなど、働く人たちのライフスタイルに対する考え方は多様です。仕事も生活も大切にしたいと思っても、現実には、「仕事か子育て」、あるいは「仕事か介護」といった二者択一を迫られる状況が多く見られます。
経済情勢や産業構造が変化する中、働き方改革が叫ばれてきましたが、労働力不足とともに長時間労働は解消されておらず、また、正規雇用者・非正規雇用者間や男女間での賃金格差により経済的自立を困難にしているといった状況も見られます。
2000年ごろから共働き世帯数が片働き世帯数を上回るようになり、最近では共働き世帯が約7割を占めるようになってきましたが、その一方で、子育て支援といった社会的基盤の整備は十分ではありません。また、根強く残る性別役割分担意識により、仕事と家事・育児・介護の両立を難しくしています。このような状況の中で、仕事と生活の両立について問題や悩みを抱えたり、長時間労働で心身の健康にも悪影響するといった事例も増えています。
こういったことから、一人ひとりが希望するバランスで、仕事と生活の調和を図ることが求められています。国では、女性、男性に関わらず、家族や育児を大切にしながら働き続けることができるよう両立支援を行うとともに、育児・介護休業法の充実を図るなど環境整備を進めています。
企業でも、ワーク・ライフ・バランスは企業・社員の双方にとってメリットがあることが認識されるようになり、育児休業制度や介護休業制度など両立支援策の充実や、柔軟な働き方ができるよう環境整備に取り組むようになってきました。
自分が希望するバランスで仕事と生活の調和を実現できれば、自分らしい生活を送ることができ、社員の働く意欲が高まるとともに、それにより企業の生産性が向上し業績拡大につながります。また、社員がボランティア活動や地域活動に参加することができることは、企業の社会的貢献にもつながり、社会全体の活力を高めることもできるでしょう。
一人ひとりが人生の段階において多様な働き方の選択ができること、また、企業や社会が多様な人材・能力を生かすことによって、ワーク・ライフ・バランスの実現につながります。
改正男女雇用機会均等法
職場で働く人が性別によって差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる環境を整備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠などを理由とする不利益取り扱いの禁止などを定めた「改正男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」)が平成19年4月1日からスタートしました。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
多様性社会推進課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番2号(文化会館2階)
電話:047-712-6803 ファクス:047-353-1145
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。